
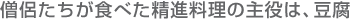
僧侶たちの重要なたんぱく源
肉を口にすることができない僧侶たちにとって、いまでも豆腐は重要なたんぱく源です。
精進料理の材料は、味噌、豆腐、ゆばなどの大豆製品をはじめ、しいたけなどの茸類や大根、ごぼうなどの野菜が多く使われます。
そもそも「精進」とは、仏教用語で、心を込めて修行することをいいます。不殺生の掟を守り、動物たちを殺してはならない僧侶たちは、日々の暮らしはもちろんのこと、食事面でも厳しい精進に身をおき、獣の肉や魚を食べず、身を清めてきました。
現在のような精進料理ができあがったのが、鎌倉時代。曹洞宗の開祖・道元は、留学先の中国から日本に戻って教えを広めていくなかで、禅僧の食事を日本の風土に合うように変えて行きました。道元は、食事をすることも料理を作ることも、みな修行であると説いたのです。
同じ頃、浄土真宗を開いた親鸞は、道元とは対照的に、仏教徒にも肉食は許されると説きました。ただし、近親者の命日は「精進日」として肉を食べないように奨励したことから、多くの人々に精進日の精進料理が広まっていったといわれています。
江戸時代に教えを説いた中国からの帰化僧・隠元は、京都の宇治に黄檗山万福寺を開き、中国風の精進料理を教えました。これが有名な「普茶料理」です。これはいまでも京都を代表する料理の一つになっています。
『精進料理献立集』は、江戸時代に出版されたものですが、この献立の約9割が豆腐を使用したもので、中でも高野豆腐を使うことが多かったようです。また、ゆばも92例中90例に使われているほどで、精進料理には欠かせない食材だったことがわかります。
ところで、精進料理には、動物の名前のついた献立が数多く見られます。きじ焼きやしぎ焼き、がんもどき、たぬきなど。肉食に対するあこがれが、肉に似た味や外見を工夫させ、料理に動物の名前をつけさせたと考えられています。



